オールコックと、富士登山
最終更新日 2023年9月23日
文・写真 森田廣海
Contents
第1章 初代英国公使オールコック
二年続けて、世界文化遺産候補の富士山に登った。
昨年の登山テーマは「富士講」。新田次郎著「富士に死す」を読んだのがきっかけだ。
長谷川角行が開き、食行身禄が発展させた富士講。江戸市中だけで八百八講もあったといわれている。あれほど興隆を極めた富士講はどうなっているのだろう?自分の目で確かめたくて吉田ルートを辿ってみた。
今年の登山テーマは「オールコック」。1860年9月、外国人として初めて富士山に登った。オールコックの登山計画に対して、幕府は、攘夷派による襲撃リスクを理由に猛反対。同年3月、井伊直弼が暗殺される桜田門外の変が起きていた。その後も攘夷活動は活発で、外国人たちを殺傷する襲撃事件が度々発生していた。外国人たちにとって非常に物騒な日本であったことは確かである。
こうしたなか、自らの命を危険にさらしてまで富士登山をした理由はなにか?富士宮観光ガイドボランティア土橋充氏に質問したところ、遠藤秀男著「富士山よもやま話」を紹介してくれたほか、オールコック著「大君の都」も読むよう助言をいただく。土橋氏のお陰で充実した富士登山のできたことを心より感謝している。
「大君の都」によると次のようであった。
1858年、江戸幕府は米、英、仏、蘭、露の各国と修好通商条約を締結した。その条文に自由な旅行の権利が謳われていたが実態はそうではなかったようだ。幕府は、攘夷活動の激化を理由として外国人たちを狭い居住地に閉じ込め、行動面にも厳しい制限を加えていたのである。老獪な幕府はその他の条文についても口実を付けて実行しなかったようだ。このままでは条約が形骸化されてしまうと危機感を募らせたのがオールコックであった。幕府の反対を押し切り、自らの命を賭して、自由な旅行の権利の行使に挑んだ。
彼を富士登山旅行に駆り立てたもうひとつの動機は貿易問題であった。幕府は、貿易の急増による物価の高騰で社会が不安定になっていると生糸、雑穀、菜種油、蝋、呉服の五品について貿易統制に舵を切ったのである。貿易統制を撤回させるには幕府の主張を覆す証拠を示す必要があった。そこで、オールコックは富士登山旅行を利用して庶民の生活をつぶさに視察し、反論材料を集めるようとしたのである。
さらに、オールコックは両手の親指がリウマチにより変形していたこともわかった。両手の親指が全く動かない状態での登山行為は相当な危険を伴ったことであろう。自らの命を危険にさらしてでも事態の打開を図ろうとしたオールコックの情熱と行動力に魅力を感じ、彼が登った富士宮ルートを辿ったのである。
| 日付 | 旅程 | 宿泊 |
|---|---|---|
| 1860年9月4日 | 横浜領事館を出発、戸塚で朝食 | 藤沢 |
| 5日 | 酒匂川の渡し | 小田原 |
| 6日 | 箱根峠を登る、箱根湯元で随行1名が温泉体験 | 箱根 |
| 7日 | 箱根峠越え | 三島 |
| 8日 | 沼津、原を経て吉原に到る | 吉原 |
| 9日 | 東海道を外れ、大宮の僧院に立ち寄り、村山に到る | 大鏡坊(村山) |
| 10日 | 山伏の案内で富士登山、石室に1泊 | 富士山中 |
| 11日 | 山頂にて位置、高度、気温等を測定 | |
| 12日 | 下山 | 大鏡坊(村山) |
| 13日 | 大宮から三島に到る | 三島 |
| 14日 | 韮山を経て熱海に到る | 熱海 |
第2章 お山開き
(1)熱海前泊
7月1日、富士宮市内で行なわれたお山開きの行事に参加。朝9時スタートのため熱海に前泊した。富士登頂に成功したオールコックも熱海に二週間近く逗留している。農漁民の生活や土地保有権、行政システム、租税などについて調べたようだ。大湯間歇泉のオールコック碑を訪ねた。オールコック碑と並んで愛犬トビーの碑もあった。間歇泉の噴湯を浴び、大火傷を負って死んだようだ。「Poor Toby」とあった。
(2)富士山開山祭神事(浅間大社)
越天楽の奏上が始まると本殿は荘厳な空気に包まれた。六名の神職が外周りの廊下をドタドタと足音を立てて渡ってくる。禅僧が音を立てずに廊下を歩むのと対照的だ。神社に参拝するとき、誰しもが鈴を鳴らし、拍手を打って神様に知らせている。宗教によって作法に違いがあるのをおもしろいと感じた。
(3)山岳救助隊夏山救助開始式(浅間大社)
本殿前庭で山岳救助隊の夏山救助開会式が行なわれた。今日から山開き、いよいよ本格稼動である。英国大使館スタッフも富士宮観光協会の半纏を着て見守っていた。
(4)護摩焚神事(大日坊)
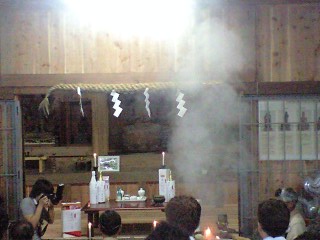 大日堂で行なわれた護摩焚神事に参加した。
大日堂で行なわれた護摩焚神事に参加した。大きな注連縄が掛かっているお堂の奥の間に五体の仏像が安置されている。大日如来がご本尊であることや護摩木を焚くのは密教の影響を受けている。修験者たちによる般若心経の読経が始まった。護摩の煙が堂内に立ちこもり息苦しくなったので堂外へ退散した。オールコックが六合目の石室に泊まった折、焚き火の煙に耐えかねて外へ避難して朝まで過ごしたくだりを思い出す。
(5)入山式(村山浅間神社)
村山登山道入口で修験者たちによるお祓い、祝詞、玉串奉奠などの神事が始まった。先ほどまで読経していた修験者たちが今度は祝詞をあげている。宗教や信仰に対するこうしたおおらかさが気に入っている。村山登山口に張られた縄を修験者が一刀のもとに切り落として山開きは終了した。神仏習合の色彩を残す一連の神事に立ち会えたことにとても満足している。キリスト教徒のオールコックが修験者の案内で富士山に登ったのもおもしろい。
(6)日英親善交流会(富士山環境交流プラザ)
富士山交流プラザに会場を移して行なわれたレセプションに参加した。
英国大使館スタッフに疑問をぶつけてみた。
- Q 英国で一番高い山はどれくらいですか?
- A 約千メートルです。冨士山のような高い山はありません。
- Q 冨士山のように夏になると大勢の人が登りますか?
- A その習慣はありません。ケーブルカーがあるのでいつでも行けます。
- Q ご挨拶の中で、「富士山の自然の美しさを尊敬するのは日本独特」とありました。自然を尊敬する文化は日本独特ですか?
- A 英国のその山はケーブルカーで行けるので身の危険を感じません。大勢の人が危険を伴っても冨士山に登ろうとする心は日本独特と思います。
- Q オールコックは9月に冨士山に登りました。その年の3月に大老の井伊直弼が攘夷派に暗殺されたほか外国人への襲撃事件も頻繁に起きていました。そうした危険を顧みず富士山に登ろうとした理由はなんだと思いますか?
- A 彼は日本の最初の公使に任命されて、とてもわくわくしていたと思います。自分の力でいろいろやれるのは嬉しいことです。他の外国人がまだやっていなかったので危険を承知で登ったのだと思います。
- Q 公使の職責は日英間の貿易振興、特に綿織物や毛織物など産業革命で大量に生産された工業製品の輸出拡大であったと思います。富士登山は輸出拡大にどのような貢献があったのでしょうか?
- A 公使にとって輸出の仕事はとても大切でした。でも、富士登山は輸出とは関係ないと思います。
- Q オールコックは大君の都に富士登山の目的を書いています。彼が本国に送ったレポートには大君の都に書けなかったようなことも書かれているような気がします。それらのレポートはどこに保管されていますか?
- A 国立図書館にあると思います。必要な手続きをすれば見られるかもしれません。
第3章 富士宮口から山頂へ
(1)当初の登山計画
1泊2日の登山計画を立てた。臨機応変な変更を想定して、山室の予約はしていなかった。
| 日付 | 旅程 | 宿泊 |
|---|---|---|
| 8月4日(木) | 富士宮⇒五合目⇒七合目 ・浅間大社へ安全祈願 ・御霊水汲み(ペット8本分) ・バスで富士宮口五合目へ ・七合目山室宿泊 | 富士宮発 14:55 五合目着 16:25 |
| 5日 | 七合目⇒山頂 ・八合目でご来光 ・山頂郵便局で投函 | 七合目発 4:00 山頂着 8:00 |
| “ | 山頂⇒五合目⇒富士宮 ・昼頃までに下山 ・浅間大社へお礼参り | 五合目発 11:30 富士宮着 12:35 |
(2)富士宮口五合目へ到着
五合目までの富士急バスは乗客が7人しかいなかった。白人が1人、インド人のグループが5人、それに私である。五合目レストハウスもすいていた。昨年の吉田口にあれほど大勢押しかけていた中国人たちがひとりもいない。やはり、原発事故が影響しているのだろうか?ところで、富士宮口のマイカー規制に問題があると感じた。片側1車線しかない狭い富士スカイラインのいたるところにマイカーが放置されている。車を置いて登山しているのだろうか?大型バスがすれ違うとき通行の邪魔になって大渋滞が発生していた。登山期間中を通してマイカー規制をやるべきだ。放置されていたのは静岡、浜松、名古屋、岐阜、滋賀ナンバーなど、中部以西からの車が圧倒的に多かった。江戸時代、中部以西の富士講は富士宮ルートを登ったがその伝統は今も続いていた。
(3)六合目雲海荘に投宿
17時、薄い空気に身体を慣らしてからゆっくりと登り始める。頂上までよく見える。この天気なら七合目まで行けそうだ。昨年の10月初旬、六合目から宝永山の近くまで登っていたので安心感もあった。 六合目に30分ほどで到達した。雲海荘に入り、オールコックの泊まった石室はこちらかと尋ねる。泊まった場所まではわからないという答えだった。また、これまでオールコックについて質問されたこともないそうだ。ほかの人はどんな目的で富士山に登るのだろう?これほど貴重な文化遺産がありながら知らずに登るのはもったいない。18時、雲海荘を後にした。下の方からガスがどんどん吹き上がってくる。南東からの風は強く、いまにも雨になりそうだ。これから登るのは私ぐらいなので少し心細くなった。20分ぐらいも登ったであろうか。だんだん風雨がひどくなり、日没も迫っている。遭難の二文字が頭をよぎり、怖くなって雲海荘へ引き返した。
夕食をとっていると下山途中の議員さんが入ってきた。若い頃、この山室でアルバイトをしていたそうだ。富士宮ルートも下山用の道を作って渋滞を解消しなければならないと訴えていた。確かに、山室にとって下山道ができると売上に影響するだろう。しかし、山室の利益ばかり優先していては登山客から見放されるだろう。富士宮ルートの活性化に熱弁をふるう議員さんの話に耳を傾けた。富士宮ルートの山室に富士講に関する説明書きのないことも指摘していた。世界文化遺産の申請骨子である富士講についてPR不足だと私も感じていた。「文化遺産の質や量という点で鎌倉は強敵です。がんばってください」と激励した。
(4)小雨のなか出発
雲海荘の宿泊客は私ひとりだったので静かに、ゆったりと寝ることができた。いつものように2時に目が覚める。強い風雨が屋根をたたきつけている。天気を心配しながら再び眠りについた。4時30分、六合目を通る登山客たちの声で目が覚めた。洗面を済ませ、持参のアンパンを頬張る。これまで消費した御霊水は2本。あと6本残っている。雲海荘の外へ出ると小雨が降っていた。飛びながら鳴く鳥の声がするので天気の回復を祈りながら出発した。
(5)オールコックの泊まった石室を探す
七合目への道も結構きつかった。喘いでは休み、休んでは喘ぐ苦難が続く。ようやく山室に辿りついた。でも、看板をみてがっかり。なんと、新七合となっているではないか。七合目の山室はさらに上方ということになる。五合目と六合目が近いのに、六合目と七合目をこれほど離すのはいかがなものか。不満をいっても始まらない。気を取り直してオールコツクの石室を探す。新七合目御来光山荘で所在を聞いたがわからなかった。次の元祖七合目山口山荘でも聞いてみたが答えは同じであった。世界文化遺産の推薦書原案にオールコックの富士登山についても触れている。肝心の山室関係者は、誰一人として彼の泊まった石室の場所を知らない。行政は文化遺産の申請に熱心に取り組んでいるが、山室関係者の教育にもっと力を入れてほしいと思った。行政と現場の意識に大きな隔たりのあることを知った。
(6)学生たちとの出会い

元祖七合目を過ぎてから下をみると雲海が広がっていた。雲の切れ間から駿河湾が望めた。頂上も快晴だ。ご来光は仰げなかったがまあまあの天気に恵まれそうだ。下山してくる人たちに山頂の様子を聞いてみた。体調が悪くなり、断念して下りてきたとのこと。未明の激しい雨に打たれながら登ったのがよくなかったといっている。六合目の山室に避難したのは正解だった。八合目の山室が小さく見えている。昨年のような登山ツアーと違ってひとり登山はペースがわからない。減量に失敗していたので途中でバテそうな気もする。悪魔の囁きが聞えてきた。「もう限界だ。オールコックが登ったのは51才、今のお前より十も若かった」。一瞬、気持ちが折れそうになった。そのとき、びわこ毎日マラソンで優勝したあるランナーの話を思い出す。「ゴールは42.195キロのかなたにある。最初からゴールを目標にして走ったら完走も難しい。目標は前方の電柱。次の電柱まで走ろう。その電柱まできたら次の電柱を目標にしてまた走る。こうした積み重ねでなんとか42.195キロが走れるのだ」と教わった。早速、適用してみた。「次のコーナーまで頑張ろう」。「あの岩で休もう」。自分で自分を励ましながら一歩ずつ登り続けた。
登山客の邪魔にならないよう登山道から少し離れて休んでいると3人連れの学生たちが倒れこんできた。「疲れたぁ~。頂上まで行けるかな?」とかなり苦しそうだ。オールコックを知っているかと尋ねると一人が知っていた。彼の成し遂げた富士登山の目的を興味深そうに聞いていた。「おれたちはなんのために登っているんだろう?」と一人が問いかける。「なんだろう?でも、山頂まで登れなかったら社会人になってもやってゆけないような気がする。」と別の一人がいう。内定を勝ち取った学生たちに余計な助言をしてしまった。「富士登山の厳しさや苦しさに較べたら会社はうんと楽だよ。それに、登山は条件が平等だけど会社は違う。ブルドーザーに乗って楽に登ってくる幸運なやつもいる」。学生たちと抜きつ抜かれつしながら八合目へ到着した。
(7)山頂へ到達
九合五勺に到着。足の筋肉がすっかり固くなっているので休憩の間もずっと揉んでいた。ここからの登りが一番きつかった。
疲労困憊でつま先が持ち上がらない。登山道に張られたロープを掴み、腰で腿を持ち上げるようにして登った。オールコックも体験したであろう最後の難関だ。「九仞の功を一簣に虧く」という諺を思い出す。ここで下山することになったら後悔しか残るまい。最後の力を振り絞り、一歩ずつ這うように登った。10時10分、ようやく富士宮口山頂に到達。山頂に立ったオールコックの姿を頭に描いてみた。日本のシンボルである富士山を征服した誇らしげな表情のオールコック。「幕府との交渉を成功させるぞ!」と叫んだかもしれない。山頂にユニオンジャック旗を立てたであろうか?「大君の都」によると富士山の位置や噴火口の大きさのほか山頂の気圧や温度も測定したようだ。自らの命を賭して登頂したオールコック公使に敬意を表したい。
(富士山頂郵便局)
●所要時間
8月4日(木) 17:00 五合目発 → 18:00 六合目発 → 18:30 六合目帰着
8月5日(金) 4:50 六合目発 → 5:41 新七合目着 → 6:37 元祖七合目着 → 7:34 八合目着 → 8:36 九合目着 → 9:10 九合五勺着 → 10:10 山頂着 → 13:43 五合目下山
富士山基本データ | 霊峰「不二」 | 富士山の歴史 | 富士山登山準備 | 持ち物 | 富士山登山ルート | 富士山・山小屋情報 | 麓から | 周辺地域から | 山から | 東京から見る富士山 | 富士山新五合目 | 登山・下山の途中で | 頂上から | 富士山周辺情報(見る) | 富士山周辺情報(遊ぶ) | 富士山周辺情報(食べる) | 富士山周辺情報(泊まる) | 富士山周辺情報(温泉) | 日本各地のご当地富士 | 関東の富士見百景 | 富士登山記



















