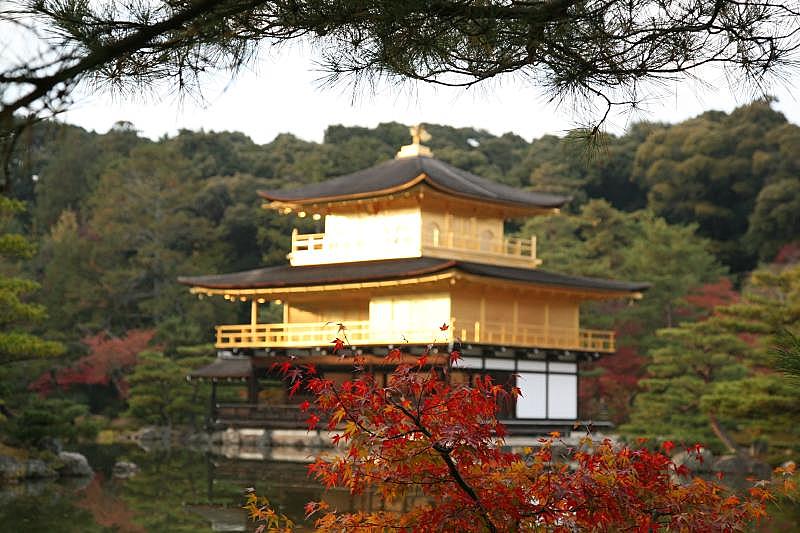岐阜大仏
最終更新日 2023年6月23日

岐阜大仏は、織田信長ゆかりの岐阜城のほど近く、岐阜県岐阜市の黄檗宗金鳳山正法寺に鎮座する釈迦如来像です。周囲1.8メートルの大イチョウの木を真柱とし、木材で骨組みをし、その周囲に竹材を編んで粘土を塗り、紙を貼り、さらに漆を塗って金箔を貼って作られた乾漆造で、像高13.63メートルと、乾漆仏としては日本一の大きさを誇ります。
江戸時代、正法寺の第11代惟中和尚が、度重なる地震や飢饉に心を痛め、これらの災害で亡くなった人々を弔うために、奈良の大仏に倣い、釈迦如来像の建立をしようと思い立ったのがその建立のきっかけと伝わっています。
惟中和尚は大仏建立の資金集めの為、各地を托鉢して歩き、時には信越地方にまで足を運んだといわれますが、発心より25年後に志の半ばで亡くなっています。和尚没後、第12代肯宗和尚がその遺志を継ぎ、1832年(天保3年)にようやく完成しました。惟中和尚が建立を思ってから、実に38年後のこと。大仏の開眼法要は、織田信長の居城以来の盛大な儀式であったといいます。
今や、世界的にも有名な「奈良の大仏」や「鎌倉の大仏」と比較すると、建立からの歴史が浅い為か知名度はそれほど高くはないですが、のんびりとした平和な空気に包まれた中に座す穏やかな大仏様です。

岐阜大仏の大仏殿
奈良の大仏の座す東大寺大仏殿と比べるとこじんまりとした印象の建物ですが、不思議と温かな雰囲気に包まれています。

大仏殿正面
正法寺は京都の宇治黄檗山萬福寺の末寺にあたります。黄檗宗は、臨済宗、曹洞宗に次ぐ禅宗の一つで、江戸時代初期の1654年(承応3年)、中国から招聘された中国臨済宗の隠元禅師によって始まった宗派で、この建物からも中国の様式が感じられます。正法寺敷地内にある「香芳苑」では、隠元禅師が中国から日本に伝えたという料理「普茶料理」が楽しめます。(要予約)

像高13.63メートル、顔の長さ3.63メートル、目の長さ0.66メートル、耳の長さ2.12メートル、口幅0.70メートル、鼻の高さ0.36メートル。木材と竹材の骨組みの上に粘土を塗って、その上に一切経、阿弥陀経、法華経、観音経などが糊で張ってあります。その上に、漆、そして金箔という構造。胎内仏として、室町時代、美濃国厚見郡革手(現・岐阜市正法寺町)の革手城下にあった、霊正山正法寺の本尊薬師如来像が安置されています。

見る角度によっては穏やかに微笑んでいるようにも見えます。目を引く大きな耳たぶは仏の身体に備わっている特徴「三十二相八十種好」の一つ。





Japan web magazine’s recommend
岐阜大仏(ぎふだいぶつ)(正法寺) DATA
- 場所: 岐阜県岐阜市大仏町8
- 交通(公共交通機関で): 岐阜駅・名鉄岐阜駅より岐阜バスで岐阜公園、長良橋方面のバス(高富行き等)で「岐阜公園歴史博物館前」バス停下車、徒歩5分。片道210円。
- 交通(車で): 東海北陸自動車道岐阜各務原ICから車で20分。
- 駐車場: あり(数台)
- 期間: 通年
- 時間: 9:00~17:00
- 休み: 無休
- 料金: 大人 200円、小人 100円
- 問い合わせ: 058-264-2760